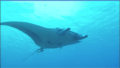筆者は、平成7年度に1級土木施工管理技士に合格しましたが、その当時には1級土木第二次検定の経験記述の参考になるサイトがほとんどなく、参考書と現場経験と前年度の問題形式に沿って解答を3種類(工程、品質、安全管理)を作成、準備万端にして臨み無事に合格出来ました。
これは実際に試験に臨場すると分かりますが、もの凄い緊張感があり事前に準備していなかったら頭が真っ白になって上手く書けなかったのではないかと思います。
現在でも記述問題の解答試案はあるのですが、経験記述の具体的解答例を示してくれる所が少ないなと言う感じですね。
そこで、この資格の取得者として、拙い内容かも知れませんが具体的な経験記述解答例を示して、少しでも皆さんのお役に立てればと思い記事にしました。
さて、2016、2017と2年続けて「安全管理」が出され、2018、2019年、2020年と実に3年連続で
「品質管理」が出され、2021、2022年度は2年続けて「安全管理」、そして2023年度(令和5年度)は、2020年度以来3年ぶりに「品質管理」が出題されました。
取り敢えず、工程管理、安全管理、品質管理の具体的な解答例を記載します。参考にして下さい。
検定申込及び検定日程は下記の通りに発表されています。
【検定申込期間】
インターネット等からの申込用紙郵送販売:令和6年2月23日(金)~令和6年3月28日(木)
対面による窓口販売:令和6年2月26日(月)~令和6年4月5日(金)(土日祝休み)
書面申込:令和6年3月22日(金)~4月5日(金)
インターネット申込:令和6年3月22日(金)~4月5日(金)23:59
申込漏れのないようにご注意下さい。
【検定日程】
1級第一次検定
試験日:令和6年7月7日(日)/合格発表日:令和5年8月15日(木)
1級第二次検定
試験日:令和6年10月6日(日)/合格発表日:令和7年1月10日(金)
経験記述について
2023年度は「品質管理」が出されましたね。2021、2022年度と2年続けて安全管理が出されたのでそれを予測していた人もいたでしょうが、そうは問屋が卸しませんね。
さて本題ですが、
工事の工程管理、品質管理、安全管理を現場状況での技術的課題、課題解決の為の検討項目、検討理由、採った対応処置、対応処置に対する評価を現実のものとして試験官に納得させる事が、合格のキーです。
例えは良くないですが、刑事事件で例えるなら犯人しか知り得ない情報、即ち
現場を本当にやった事がある人しか知り得ない、現実味のある体験に基づく経験記述、これが一番大事です。
多少、文章が下手くそでも、漢字を知らなくても、切実な現場実体験記述が何よりも迫力があるのです。
只、そこには専門用語の配置が必然ですし、何でも経験した事だけ単純に書けば良いと言うものではありません。
現場で体験した技術的課題です。
その問題がその工事の工程、品質、安全に大きく関わるような事を記述しないとダメです。
現場代理人が決まらないとか、協力会社が確保できないとか、そう言う単純な事を聞いているのではなく、技術的な課題です。
出題項目
当然ながら、工程管理、品質管理、安全管理がメインになります。
一時期、施工計画とか環境対策とか出た時もありましたが、その3つを前以って準備しておけば問題ないと思います。
経験記述問題のスタイルは、このような形になっていると思います。
(1)工 事 名
○○○○○○工事
受験申請時に書いた契約書通りの工事名を、正確に記載して下さい。
ただ、これは一番オーソドックスな事であって、令和6年度の1級土木施工管理技術検定申込受付期間は、令和6年3月22日(金)~4月5日(金)、1級第1次検定試験日が令和6年7月7日(日)、合格発表日令和6年8月15日(木)、更に1級第2次検定が試験日:令和6年10月6日(日)なので、極端な話、9月末工期の工事など受験申請後から2次検定試験日までに取り組んだ工事で書きたい場合もあると思います。
その場合、その工事名で経験記述を書いても実際にやったものであれば、不実記載にはならないと思います。当然、当初工事契約書もあるはずですからね。
あまり、ギリギリだと工変があった時は、変更契約書が試験の時にはないですけれど、そんなものは試験の時には不要ですし、万(億)が一、後で見せろと言われても、その時は変更契約も終わっているでしょうから、何の問題もないと思います。
又、最終設計変更数量も代理人をやった人なら自分で把握してますから、書けるでしょうしね。
筆者の時は、その間にやった工事がなかったので、オーソドックスに受験申請時の記載工事について述べました。
(2)工事の内容
発注者名 ○○市土木事務所など
工事場所 ○○市○○町地先など
工 期 平成 年 月 日~平成 年 月 日
施 工 量 工事の主要な工種と数量を列記する、全部記載する必要はない
(3)工事現場における施工管理上のあなたの立場
現場代理人、主任技術者、工事主任、工務主任等、どの設問が出ても無難に対応できる立場が良いでしょうね。
工程管理解答例
出題は、このようになっていると思います。
上記工事の現場状況から特に留意した[工程管理]に関し、次の事項について、解答欄に具体的に記述しなさい。
1.具体的な現場状況と特に留意した技術的課題
2.技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容
3.技術的課題に対して現場で実施した対応処置とその評価
1.2.3の技術的課題、解決するための検討した項目と検討理由及び検討内容、実施した対応処置とその評価を一つずつの事例でまとめて記載してみます。
1.具体的な現場状況と特に留意した技術的課題に、どんなものがあったか?
(技術的課題①)
2-1.その技術的課題に対して、どのような検討を行ったか?
(検討項目①)
②プレキャスト製品の活用(上部のヘッドスラブ、両側面のサイドウォール、底部のフーチングの4断面)
2-2.検討した理由は、何か?
(検討理由①)
②検討項目②は、検討項目①の工場受注生産より既製品である為、更に工程短縮可能となる(サイズさえ合えば)
3-1.検討した項目に対して、どのような処置を行ったか?
(対応処置①)
3-2.対応処置を行った結果は、どうであったか?
(対応処置①に対する評価)
このように、
-
現場でどんな技術的課題があり
-
それを解決するためにどのような検討を行い
-
何故そのような検討を行ったか理由を述べ
-
そして、どんな対応処置をし、処置した結果評価はどうだったか
と、一から十までよくぞそこまで根掘り葉掘り聞けるものだと感心しますが、試験ですから仕方ありません。
【2つ目の技術的課題】
1.具体的な現場状況と特に留意した技術的課題に、どんなものがあったか?
(技術的課題②)
2-1.その技術的課題に対して、どのような検討を行ったか?
(検討項目②)
2-2.検討した理由は、何か?
(検討理由②)
3-1.検討した項目に対して、どのような処置を行ったか?
(対応処置②)
3-2.対応処置を行った結果は、どうであったか?
(対応処置②に対する評価)
以上2点、具体例を挙げて見ました。
ちょっと理想っぽい点もあるかも知れませんが、書いた事柄は作り話ではありません。
また、実際の現場では、色んな事があると思いますが工事途中で起きた問題点より、着手前に予想される問題点提起した方が、工事に取り組む姿勢として評価が高いと思います。
しかし、途中途中で起きた問題も現実味があってそれはそれで良いのかも知れません。
あまり深く考えなくても良いと思いますが、そこから先は、各人でお考え下さい。
記述は、1~2点ほど問題を書くようにしたら良いと思います。あまり多すぎても焦点がボケますから。
工程短縮のキーワードとして、現場打ちからプレキャスト品の採用と言うのが他の工種でも使えると思います。
以上、工程管理についてでした。
安全管理解答例
出題は、このようになっていると思います。
上記工事の現場状況から特に留意した[安全管理]に関し、次の事項について、解答欄に具体的に記述しなさい。
1.具体的な現場状況と特に留意した技術的課題
2.技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容
3.技術的課題に対して現場で実施した対応処置とその評価
1.2.3の技術的課題、解決するための検討した項目と検討理由及び検討内容、実施した対応処置とその評価を一つずつの事例でまとめて記載して見ます。
1.具体的な現場状況と特に留意した技術的課題に、どんなものがあったか?
(技術的課題①)
2-1.その技術的課題に対して、どのような検討を行ったか?
(検討項目①)
2-2.検討した理由は、何か?
(検討理由①)
3-1.検討した項目に対して、どのような処置を行ったか?
(対応処置①)
3-2.対応処置を行った結果は、どうであったか?
(対応処置①に対する評価)
以上、安全管理についてでした。
品質管理解答例
品質管理で書き易い一般的な項目とすれば、コンクリート関係、暑中、寒中コンクリートの品質管理や、舗装関係では合材の温度管理等ですね。
出題は、このようになっていると思います。
上記工事の現場状況から特に留意した[品質管理]に関し、次の事項について、解答欄に具体的に記述しなさい。
1.具体的な現場状況と特に留意した技術的課題
2.技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容
3.技術的課題に対して現場で実施した対応処置とその評価
1.2.3の技術的課題、解決するための検討した項目と検討理由及び検討内容、実施した対応処置とその評価を一つずつの事例でまとめて記載して見ます。
1.具体的な現場状況と特に留意した技術的課題に、どんなものがあったか?
(技術的課題①)
2-1.その技術的課題に対して、どのような検討を行ったか?
(検討項目①)
2-2.検討した理由は、何か?
(検討理由①)
3-1.検討した項目に対して、どのような処置を行ったか?
(対応処置①)
3-2.対応処置を行った結果は、どうであったか?
(対応処置①に対する評価)
以上、品質管理についてでした。
【注意事項】
既にご承知の事と思いますが、安全確保の為、ガードマンの人数を増やしたとか、そんな単純な話は誰でも書けますし、そのような技術的課題はダメとなっていることはご存知と思いますが、念の為申しておきます。
又、丸写しは絶対お止め下さい、これはあくまでヒントですから。
皆が皆、同じ内容では変ですし、俺一人位と思う人が1000人居たとしたら大変ですよ。
同じような回答だと、嘘だとばれます。
なぜなら試験(採点)官同士の連携で似たような解答についても話合われる、というような話を風の噂で聞いたことがあります。
もし、そこで同一ソースと判断されれば、その時点で他の記述問題が出来ていても一発で不合格になるそうです。
虚偽記載をするような人に、国家資格を保有する資格はないという考えですね。
せっかくの苦労が水の泡です、絶対にそれだけは止めて下さい。
あくまで、実体験に基づいた真実を書いて下さい。
この記事は、先ほど申しましたようにあくまでヒントです、このように書けば必ず受かると保証するものではありません。
試験制度の再編について(令和3年度)
2021年度(令和3年度)から技術検定の再編がありました。
現行制度では、学科試験は知識問題、実地試験は能力問題で構成されていましたが、新制度では、
第一次検定では、知識問題を中心に能力問題が追加され、第二次検定では、能力問題を中心に知識
問題が追加されます。
第一次検定では、監理技術者補佐として、工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識及び応用能力を有するか判定。(これまで学科試験で求めていた知識問題を基本に、実地試験で求めていた能力問題の一部を追加)
第二次検定では、監理技術者として、工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識及び応用能力を有するか判定。(これまで実地試験で求めていた能力問題に加え、学科試験で求めていた知識問題の一部を移行)
問題1の経験記述には、もちろん変更はなしですが
選択問題①(問題2から問題6までの5問中、3問選択解答)
選択問題②(問題7から問題11までの5門中3問選択解答)だったのが、
問題2(穴埋め問題)と問題3(記述問題)の計2問が必須となり、
選択問題①(問題4から問題7までの4問中、2問選択解答)は、穴埋め解答
選択問題②(問題8から問題11までの4問中、2問選択解答)は、すべて文章で答える記述式問題と言う形式に変わりました。
具体的には、「施工管理の基本となる施工計画の立案に関して、下記の5つの検討項目における検討内容をそれぞれ解答欄に記述しなさい。」と言うものでした。
-
契約書類の確認事項
-
現場条件の調査(自然環境の調査)
-
現場条件の調査(近隣環境の調査)
-
現場条件の調査(資機材の調査)
-
施工手順
以上になります。
これらは設問にある通り施工計画作成上において、契約書類の確認、現場事前調査は施工管理に携わる者にとって必須の確認事項で、これらを調べておかないと施工計画が書けませから、監理技術者としての知識を問う事項とすれば当然の事と思われます。
今年は、施工計画の立案上の調査・確認事項について問うものでしたが、「監理技術者としての知識を問う問題」と言う観点からすれば、他にも考えられますので来年もこの内容で出る可能性は低いのではないかと思います。
他には、「建設業法上での監理技術者として遵守すべき事項」なども考えられます。
まとめ
最後にもう一度経験記述のポイントを言いますが、
現場を本当にやった事がある人しか知り得ない、現実味のある体験に基づく経験記述、これが一番大事です。
あ~これは実際にやってないな、作り話だなと判断されたら、難しいと言う事です。
これも、風の噂で試験官のつぶやきを聞いた事がある人から、聞いた話ですけどね。
資格を取るのは、容易な事ではありませんが、努力した時間の多寡と真の経験がものを言うのではないでしょうか。
頑張って下さい!!
1級造園施工管理技士実地試験に関する記事もupしましたので、ご関心のある方はご覧になってください。